脳神経内科では、脳、脊髄、末梢神経さらに筋肉に関わる疾患を扱います。非常に多岐にわたりますが、代表的な例は次のようなものです。
その他、以下のセカンドオピニオン外来も行っています。
※多発性硬化症セカンドオピニオン外来
毎週水曜日の午後に新野/宮﨑医師による「多発性硬化症専門外来」(セカンドオピニオン外来)を実施しています。
【脊髄性筋萎縮症に対するスピンラザⓇ治療のお知らせ】
北海道医療センターでは、主に、成人のSMA患者さんに、スピンラザⓇの髄腔内投与を行っています。
脳神経内科医師と、麻酔科医師、整形外科医師、放射線技師、薬剤師、リハビリテーション部門、検査部門が一体となって、安全・確実にスピンラザの投与と効果判定を行います。
詳細はこちら
【パーキンソン病のDAT治療(device aided therapy)】
当院では症状の日内変動でお困りのパーキンソン病患者さんを対象に、レボドパ・カルビドパゲル持続経腸療法(デュオドーパ🄬)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ持続皮下注射療法(ヴィアレブ🄬)を行っています。関心のある方は主治医の先生とご相談の上、事前に予約して受診してください。
| 氏名・職名 | 認定資格 | 主な専門分野 |
|---|---|---|
| みなみ なおや 南 尚哉 内科系診療部長 認知症疾患医療センター副センター長 難病診療センター・ チーフコーディネーター |
|
重症筋無力症 神経変性疾患 |
| にいの まさあき 新野 正明 臨床研究部長 セーフティネット診療部長 神経免疫疾患センター長 認知症疾患医療センター長 難病診療センター長 小児慢性特定疾病・在宅・ 移行期医療支援センター長 |
|
多発性硬化症 視神経脊髄炎 認知症 |
| あきもと さちこ 秋本 幸子 医長 |
|
パーキンソン病等の 神経変性疾患 臨床神経学一般 |
| みやざき ゆうせい 宮﨑 雄生 臨床研究副部長 医長 |
|
多発性硬化症 視神経脊髄炎 認知症 |
| あみの いたる 網野 格 医師 |
|
臨床神経学一般 てんかん 重症筋無力症 |
| すぎむら ようこ 杉村 容子 医師 |
|
脳神経内科一般 認知症 |
| うわとこ めぐみ
上床 恵 医師 |
|
脳神経内科一般 |
| みやぎし まい 宮岸 麻衣 医師 |
脳神経内科一般 |
MRI・CT・SPECTなどの画像診断機器および、脳波、神経伝導検査、針筋電図などの電気生理学的検査
入院 (延べ) |
外来 (延べ) |
|||
|---|---|---|---|---|
延総数 |
715名 | 8042名 | ||
重症筋無力症関連 |
231 | 32% | 2218 | 28% |
パーキンソン病関連疾患 |
82 | 11% | 1027 | 13% |
多発性硬化症関連疾患 |
76 | 11% | 1138 | 14% |
運動ニューロン関連疾患 |
46 | 6% | 107 | 1% |
てんかん |
9 | 1% | 304 | 4% |
脊髄小脳変性症・多系統萎縮症 |
34 | 5% | 188 | 2% |
末梢神経疾患 |
9 | 1% | 249 | 3% |
感染症・炎症性疾患 |
49 | 7% | 411 | 5% |
筋疾患 |
21 | 3% | 145 | 2% |
認知症(アルツハイマー含む) |
22 | 3% | 671 | 8% |
スモン |
0 | 0% | 34 | 0% |
頭痛 |
1 | 0% | 311 | 4% |
その他 |
135 | 19% | 1239 | 15% |
2024年度臨床研究業績一覧(著書・総説・原著・症例報告・講演・学会発表)
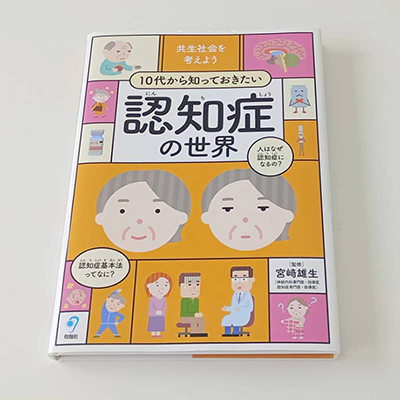
現在、高齢者の8人の1人が認知症とされ、今後、ますますその数は増えていきます。 2024年には認知症基本法も施行され、認知症という病気が「当たり前」の社会を私たちはこれから生きていきます。 認知症とはそもそもどんな病気なのか。どう向き合えばいいのか。 認知症の人たちとの共生社会を若い世代といっしょに考えていきます。
宮﨑雄生 監修 旬報社 出版年月日 2025/02/27 ISBN 9784845119707
当科の前身は旧国立札幌南病院にあって、そこでは昭和54年に標榜科としての神経内科が、北海道で初めて開設されました。当時から神経難病のパイオニアとして診療に当たってきましたが、2010年に現在の地に移ってからは、慢性疾患だけでなく急性期の神経内科疾患にも幅広く対応しています。また、総合病院の神経内科ですので、他科とも連携して他疾患による神経内科的症状にも対応しています。さらに、神経疾患は治療が確立していない疾患も多いことから、少しでも早く薬が使えるよう、当科では積極的に治験に参加しています。詳細は“現在行っている治験”をご覧ください。今後も近隣の諸施設をはじめとした多くの医療機関のご協力を得ながら診療に励んでいく所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。神経内科疾患が疑われる場合などもお気軽にご相談ください。
