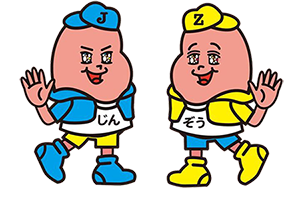
腎臓内科が作成した腎臓病に関する読み物です。
腎臓内科が作成した腎臓病に関する読み物です。
尿には、ほとんどタンパク質は漏れませんが、尿にタンパクが含まれていると健診などで、尿蛋白陽性(+〜4+)を指摘されて、内科受診を勧められます。腎臓内科では尿蛋白量をU-TP/U-Creという項目で調べます。0.15g以上が異常です。3.5g以上だとネフローゼ症候群が疑われます。尿蛋白が多く出続けると腎機能が徐々に悪くなることがあります。
腎性貧血の薬といえば、注射薬のエリスロポエチン製剤でしたが、最近内服製剤が発売されました。低酸素誘導因子(HIF)を分解されにくくする薬で、体内のエリスロポエチンを増加させます。治療目標はHb11前後です。投与は毎日か週3回服用します。鉄不足になる場合は、鉄剤も併用します。
HIF-PH阻害薬の種類:ダーブロック、エベレンゾ、 バフセオ、エナロイ、マスーレッドなど
「息切れ」は、腎臓病に特有の症状ではありません。また原因も様々です。腎臓病の方で「息切れ」が出る理由は主に貧血によります。ネフローゼなどでむくみや胸水などの体液過剰を認める場合にも「息切れ」することもあります。貧血が原因であれば、貧血の治療が必要です。体液過剰の場合は、塩分制限や利尿剤投与が必要となります。薬だけで対応できない場合は、透析治療が必要となる場合もあります。
食べ物解説:スイカ
夏はスイカの季節です。「スイカは腎臓に良い」という話を聞いたことはありますか。
スイカは水分とカリウムが多く含まれており、腎機能が良い方にとっては、尿が出ていいのかもしれません。
腎機能が悪い方にとっては、カリウム値が上昇してしまい、不整脈や突然死の原因となってしまうかもしれないので、食べ過ぎ注意です!
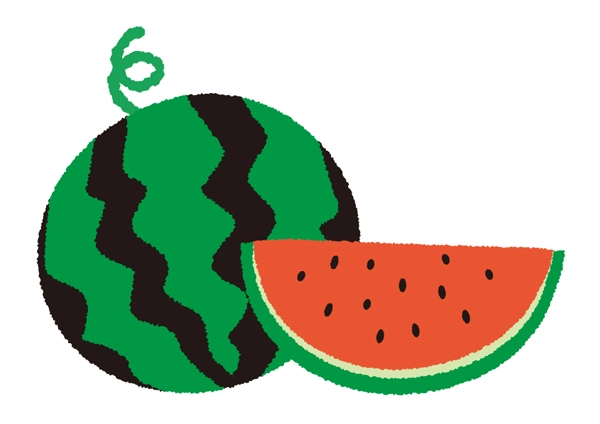
スイカのカリウム量100gあたり120mg
サイコロ状のカットスイカ3個で約100g
カリウム制限は1日1500〜2000mg
2024年9月
北海道医療センター
腎臓内科 医長 柴崎 跡也
慢性腎臓病の悪化による透析導入患者数はいまだに減少していず、厚労省は年間の新規透析導入患者数を35,000人以下にするという数値目標を設定し、全国の医療機関で慢性腎臓病の重症化予防に取り組んでいます。当院は西区の腎臓内科施設として、慢性腎臓病の重症化予防に力を入れ、病診連携を行っております。
